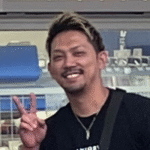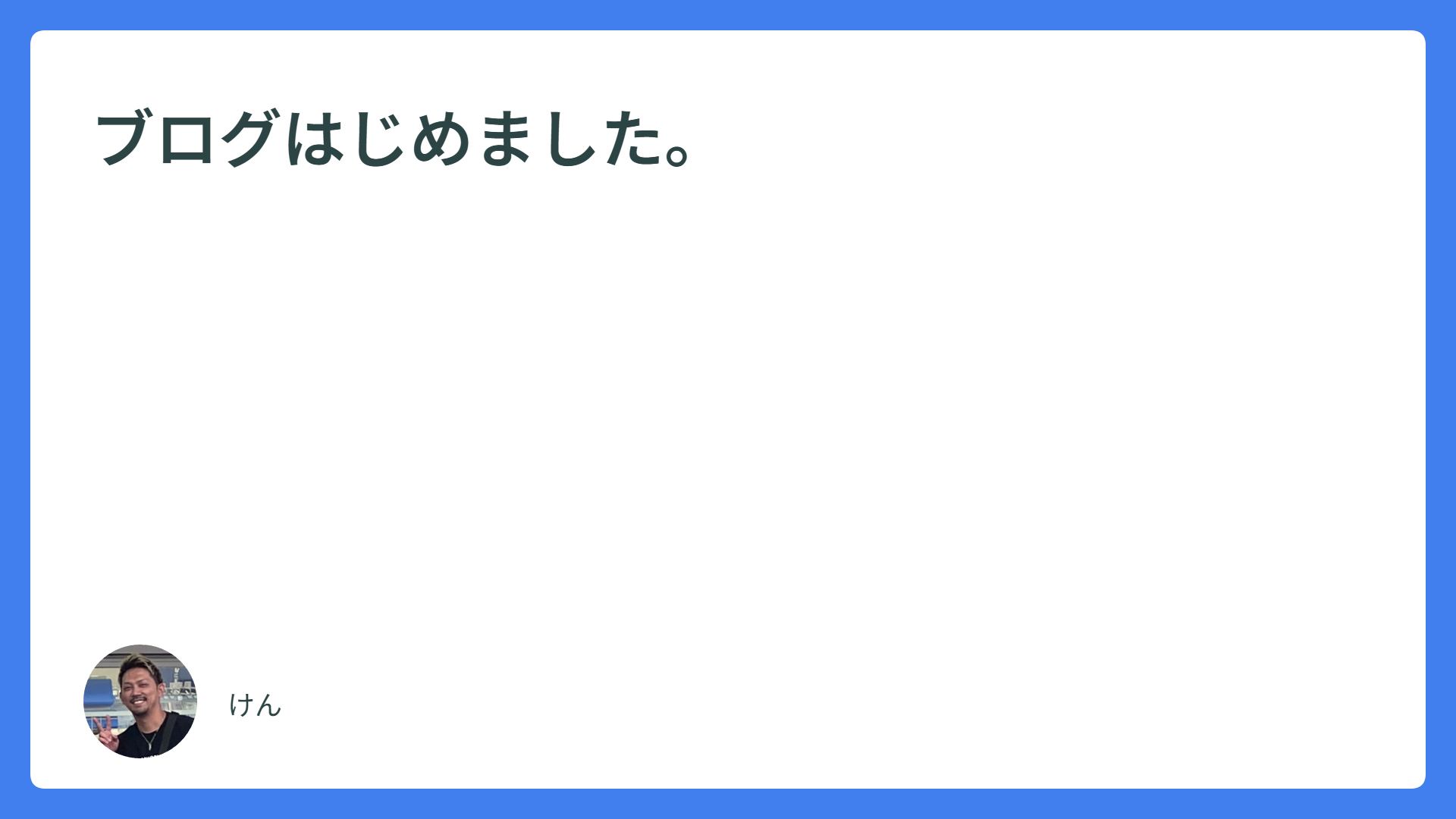P&G流マーケティング実践論|成果を出す3つのポイント

はじめに|日本の”技術はあるのに売れにくい”課題
こんな悩みを抱える日本企業は少なくありません。実際、多くの日本企業が陥っているのは、技術偏重から始まる負のスパイラルです。
技術偏重 → 顧客起点不足 → 価格競争 → 利益出ず投資できない
この悪循環から抜け出すには、発想の転換が必要。
正直、私自身も物販ビジネスを始めた当初は「良い商品を作れば売れる」と思っていました。しかし現実は違った。商品力だけでは限界があることを痛感したのです。
そこで学んだのが、(ここは下線)マーケティング=売れる仕組みを創ることという考え方。
単に宣伝することではなく、営業が頑張らなくても自然と商品が売れる状態を設計すること
これがマーケティングの本質です。
今回は、世界的に成功しているマーケターたちの手法を日本企業でも実践できる形にまとめました。技術は一級なのに売上に悩む企業こそ、この記事を読んでほしい。
「売れる仕組み」をつくる3つのコントロール

売れる仕組みを作るには、3つの要素を同時にコントロールする必要があります
どれか一つだけでは不十分。全体設計が重要です。
顧客の頭の中(認知・ブランド想起)
最も重要なのが、お客さんの頭の中を理解し、コントロールすること。
商品名を聞いた瞬間に「あ、あれね」と具体的なイメージが浮かぶ状態。これがブランド想起です。
例えば「宅配ピザ」と聞いて、どんなブランドを思い浮かべますか?
おそらく特定の企業名と、その特徴(「30分で届く」「チーズがとろける」など)がセットで浮かんだはず。これが理想的な認知とブランディングの状態です。
店の棚/チャネル×価格(Place×Price)
お客さんが「欲しい」と思った時に、適切な場所で、適切な価格で商品が手に入る状態を作ること。
ターゲット顧客の行動パターンを理解し、彼らが商品を探す場所に商品を置く
そして、価値に見合った価格設定をする。
安易な値下げは思考停止。むしろ価値を高めて適正価格で売ることが、持続的成長の鍵となります。
体験(Productの満足とリピート)
ここでのポイントは「少し超える」という部分。完璧を目指しすぎると、コストが膨らみ、スピードが遅くなります。
重要なのは、お客さんが抱いた期待を適度に上回る体験を継続的に提供すること。これがリピーターを生み、効率的な売上拡大につながります。
「営業が売り込む前から”売れやすい状態”を設計する。」
これこそが、マーケティングの真の価値。営業の負担を減らし、組織全体の生産性を向上させる仕組みです。
P&G流「ジョブ」と「不」から始める戦略設計

世界的に成功している企業のマーケターたちは、共通して「顧客の未解決の課題」から発想を始めます。この課題を「ジョブ」と呼びます。
顧客の未解決ジョブを特定する
マーケティングで最も重要なのは、「誰が」(Who)ではなく、「何に困っているか」(不)の特定です。
不便・不満・不安といった顧客の「不」を見つけることから、すべてが始まります。
例えば、台所用洗剤の成功事例では「排水口を毎日除菌したいが
漂白剤は強すぎて使いにくい」という潜在的な不満を発見
この「不」を解決する商品として既存の洗剤を再定義し、大きな成果を上げました。
顧客は自分の課題を明確に言語化できません。だからこそ、定性調査や行動観察を通じて、生活文脈の中から「不」を読み取る必要があります。
売上の三つのテコ(認知率・購入率・購入単価)
売上を分解すると、以下の3つの要素に集約されます:
- 認知率:ターゲット顧客のうち、商品を知っている人の割合
- 購入率:認知している人のうち、実際に購入する人の割合
- 購入単価:一人当たりの平均購入金額
まず、この3つのうちどれに最も伸びしろがあるかを特定。そこにリソースを集中投下することが短期的な戦略となります。
すべてを同時に改善しようとすると、リソースが分散して効果が薄くなります。
POD(Point of Difference)で”選ぶ必然”を作る
競合商品との差別化ポイント。これがPOD(Point of Difference)です。
PODは「顧客が求めていて、かつ競合が持っていない利点」でなければなりません。これがないと価格競争に陥ります。
POD創出の3つのアプローチ:
- 再解釈:既存の特徴に新しい視点を加える
- 組み合わせ:複数の価値を組み合わせて新しい便益を作る
- カテゴリ利点の極大化:特定分野で圧倒的なレベルまで品質を高める
私の経験でも、物販で成功した商品は必ず明確なPODがありました。「なぜこの商品を選ぶのか?」が3秒で説明できない商品は、結果的に売上が伸び悩みます。
伝わるコミュニケーション(想起・独自性・POD伝達)
どんなに優れたPODがあっても、それが顧客に伝わらなければ意味がありません。
効果的なコミュニケーションの3要素:
- ブランド想起:どのブランドの広告かすぐ分かる
- 独自性:他とは違うユニークさで記憶に残る
- POD伝達:差別化ポイントが一目で理解できる
また、顧客の購買プロセス(カスタマージャーニー)に応じて、最適なメディアを選択することも重要:
- ペイドメディア(広告):認知・訴求段階で効果的
- オウンドメディア(自社メディア):既存ファンとの関係深化
- アーンドメディア(口コミ・SNS):購入・推奨段階で強力
- 接触施策(試食・体験):購入率向上に直結
データ駆動で意思決定|”感覚”から”再現性”へ

「なんとなく売れている」「なんとなく売れていない」から脱却し、再現性のある成長を実現するには、データ駆動の意思決定が不可欠です。
計測設計(KPIツリー)
売上に至るまでのプロセスを数値で分解し、可視化すること。
基本的なKPIツリー例: Impressions(表示回数)→ CTR(クリック率)→ CVR(購入率)→ ARPU(平均単価)→ LTV(生涯価値)
このように分解することで、問題が発生した際に「どこに原因があるか」を即座に特定できます。
さらに、媒体別・セグメント別に細分化することで、より精度の高い分析が可能になります。
原因特定の手順化(誰でも回せる)
数値に異常が発生した際の原因特定プロセスを標準化することで、属人的でない分析体制を構築できます。
基本手順:
- 日次データで前日・前週との比較
- 表示回数・CTR・CVRのどこに問題があるかを特定
- 問題箇所をさらにドリルダウン(媒体別・商品別など)
- 考えられる原因をチェックリストで確認
重要なのは「まずデータで事実確認」を文化化すること。感情的な憶測ではなく、客観的な数値から議論を始める習慣です。
未来逆算と投資判断
データの蓄積により、将来の売上予測も可能になります。
予測ロジック: 新規獲得数 × 継続率 × 平均単価 = 将来LTV
この計算により、短期的には赤字でも、長期的に利益が出る投資判断ができるようになります。
例えば「今月1000人の新規顧客を獲得するために50万円投資すれば、3年後に300万円の売上になる」といった論理的な投資判断が可能です。
人とシステムの役割分担|仕組み化と”法則発見”

データ駆動を実現するには、人間とシステムの適切な役割分担が重要です。
システムの役割
定型的な分析はすべてシステム化し、自動化すること:
- 日次データの監視とアラート
- KPI異常の一次検知
- 原因特定のためのチェックリスト提供
- レポートの自動生成
これにより、誰でも一定水準の分析ができる環境を整備。属人性を排除し、再現性を確保します。
人間の役割
一方、以下の領域は人間が担当:
- 非定型の仮説生成:過去のパターンにない新しい要因の分析
- 法則性の発見:データから新しい成功パターンを見つける
- クリエイティブ判断:広告やページデザインの定性的評価
- 戦略立案:中長期的な方向性の決定
ぶっちゃけ、この領域では個人の適性が大きく影響します。データ分析から法則性を見つけることに喜びを感じる人と、そうでない人では、成果に大きな差が生まれます。
採用>教育の重要性
多くの企業で見落とされがちですが、適性に合う人を最初から配置することが、教育よりも重要です。
データ分析が得意な人、クリエイティブが得意な人、顧客との対話が得意な人。それぞれの強みを活かせるポジションに配置することで、組織全体のパフォーマンスが向上します。
私自身の経験でも、「頑張れば誰でもできる」と考えていた時期がありました
しかし、実際には個人の適性による差は歴然としてあります
この現実を受け入れ、適材適所の配置を行うことが、
結果的に全員の幸福度向上にもつながります。
B2C/B2B/中小・SaaSでも使える実装テンプレ

30日実装ロードマップ(保存推奨)
Week 1:顧客”不”の棚卸し/ジョブ仮説
- 既存顧客へのヒアリング(購入理由・不満点)
- 競合商品の口コミ分析
- 「不便・不満・不安」の分類整理
- 解決すべきジョブの仮説設定
Week 2:POD仮説→検証用メッセージ・LP素案
- 競合分析によるポジショニングマップ作成
- 自社の差別化ポイント(POD)仮説
- PODを伝える3秒メッセージ案作成
- 検証用ランディングページの素案制作
Week 3:計測設計→小額配信→A/B
- KPIツリーの設計
- 広告アカウント・計測ツールの設定
- 月予算の10%程度で小規模テスト配信
- メッセージ・クリエイティブのA/Bテスト
Week 4:勝ち筋の拡張(チャネル・単価・体験)
- 成果の良い要素の特定と要因分析
- 他チャネルへの横展開
- 単価アップまたは追加商品の検討
- 顧客体験の改善ポイント抽出
チェックリスト
実装完了の確認項目:
□ ジョブ定義は実際の顧客行動で裏取りしたか
□ 認知・購入率・単価のうち最重要テコを一本化したか
□ PODが3秒で伝わるメッセージになっているか
□ KPI分解から日次異常検知までの手順が文書化されているか
□ 人とシステムの役割分担が明文化されているか
□ 各担当者の適性と業務内容がマッチしているか
□ 30日後の振り返り日程が確定しているか
このチェックリストは、B2C・B2B・SaaSなど業種問わず活用できます。自社の状況に合わせてカスタマイズしてください。
まとめ|”売れる仕組み”は設計で決まる
技術力だけでは勝てない時代。
これらすべてが組み合わさって、初めて「売れる仕組み」が完成します。
一つひとつは難しくありません。重要なのは、全体を設計思考で捉えること。
まずは**”不とジョブの1枚スライド”**を作るところから始めてみてください。あなたの顧客は、どんな「不」を抱えているでしょうか?
まとめ
日本企業の成長加速には「技術偏重→顧客起点」への転換が必須
売れる仕組みは「認知×体験×チャネル価格」の3要素コントロールで設計
P&G流の「ジョブ理論→POD→伝わるコミュニケーション」と「データ駆動の意思決定→人とシステムの役割分担」により、再現性のある成長を実現。30日実装ロードマップで即実践可能。
保存用テンプレ
実装完了の確認項目:
□ ジョブ定義は実際の顧客行動で裏取りしたか
□ 認知・購入率・単価のうち最重要テコを一本化したか
□ PODが3秒で伝わるメッセージになっているか
□ KPI分解から日次異常検知までの手順が文書化されているか
□ 人とシステムの役割分担が明文化されているか
□ 各担当者の適性と業務内容がマッチしているか
□ 30日後の振り返り日程が確定しているか