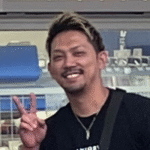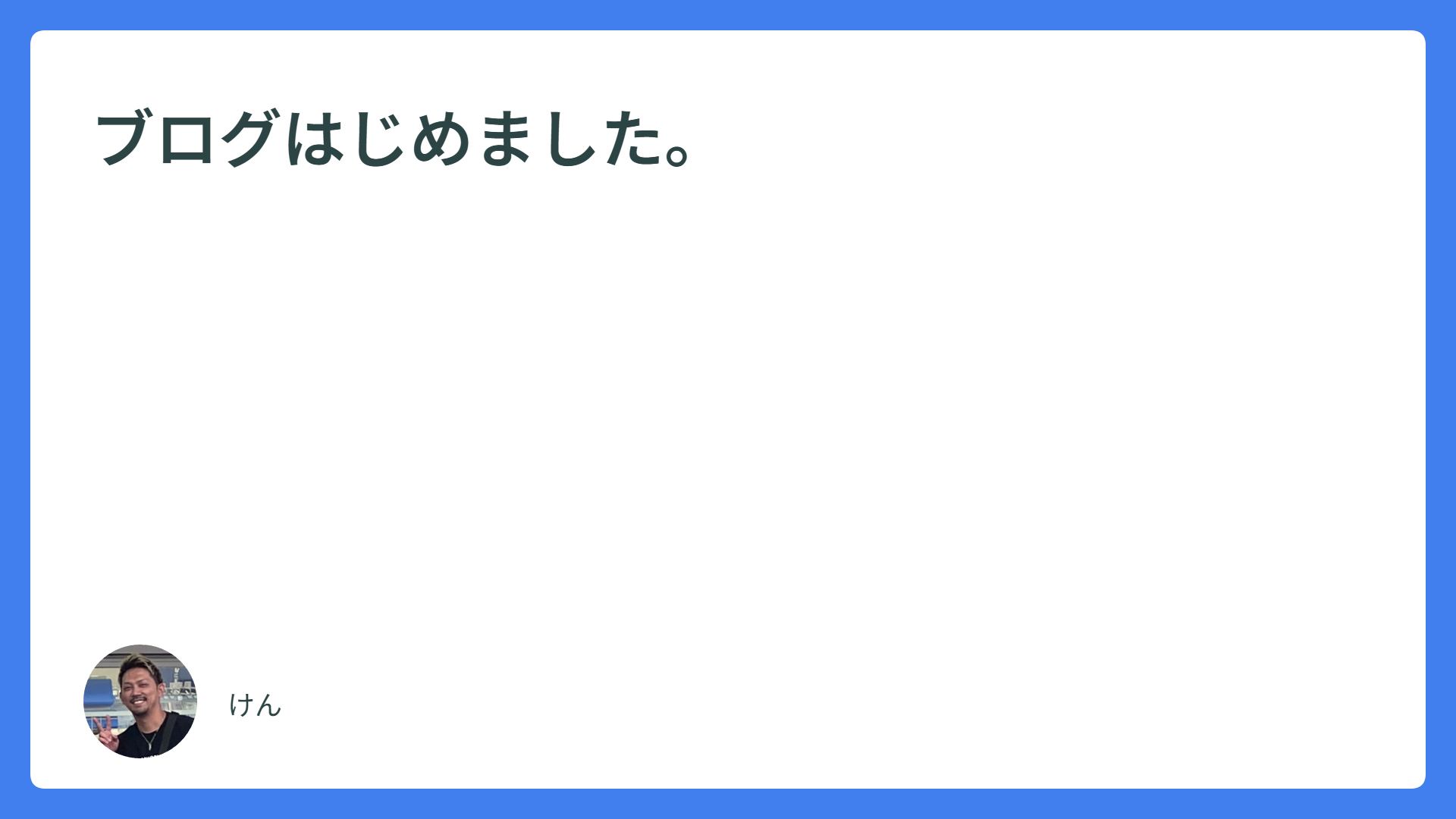90日で部下が激変|管理職がやるべき7つのアクション

部下が萎縮する職場で本当に成果は出るのか?
「また怒られるかもしれない」
そんな恐怖心を抱えながら出勤してくる部下を見たことはありませんか?
タイムカードを押す手が震えている新人。
上司の顔色をうかがいながら、言いたいことも言えずに黙り込んでしまうメンバー。
私は20年のサラリーマン経験と現在の事業運営を通じて、一つの確信を持つようになりました。
逆に言えば、部下一人ひとりに居場所を与えることができれば、組織は劇的に変わります。
萎縮していた部下が積極的に発言するようになり、指示待ちだったメンバーが自ら提案してくるようになる。
今日は、実際に私が体験した失敗と成功の実例を交えながら、部下に居場所を与えることの重要性についてお話しします。
理論ではなく、現場で起きた生々しい話。
あなたの職場でも、今日から実践できる具体的な方法をお伝えします。
はじめに|部下には居場所を与えることの大切さ

タイムカードを押すとき、ビクビクしながら出勤してくる部下
上司の目を気にして、質問したいことがあっても声をかけられない新人
会議では発言を求められることもなく、ただ座っているだけの若手メンバー
そんな光景を見たことはありませんか?
萎縮した状態では、どんなに能力があっても成長は止まってしまいます。
それどころか、貴重な気づきや改善提案も、恐怖心によって埋もれてしまう。
私自身が新人時代に経験したのは、まさにこの状況でした。
意見があっても言えない環境。
任される仕事もなく、ただ見ているだけの毎日。
その結果、チーム全体のパフォーマンスが下がり、
最終的にプロジェクトが失敗に終わったのです。
逆に「ここが自分の居場所だ」と感じられる環境では、
部下は驚くほど成長します。
積極的に発言し、責任を持って仕事に取り組み、時には上司が思いつかないような斬新なアイデアを提案してくれる。
今日は、部下に居場所を与えることの重要性と、明日から実践できる具体的な方法についてお話しします。
体験談|任せられずに失敗した過去
私が新人だった頃の話から始めさせてください。
入社3年目、ある大きなプロジェクトのメンバーに選ばれました。
業界でも注目される案件で、私は内心とても期待していました。
でも上司からは
「君はまだ経験が浅いから、様子を見ていてくれ」と言われ、
ほとんど雑用係扱い。
会議では発言を求められることもなく、ただ座っているだけ。
何か意見があっても「まだ君には早いかな」と遮られる日々が続きました。資料のコピー取り、会議室の予約、弁当の手配。そんな作業ばかりを任されていました。
でも実は、
顧客との打ち合わせで違和感を感じる瞬間があったり、競合他社の動向で気になる情報をキャッチしていたり。
でも「まだ君には関係ない」という空気感の中で、誰も声を上げることができませんでした。
結果として、そのプロジェクトは大失敗に終わりました。
後から判明したのは、私たちが気づいていた問題点が実際に致命的な欠陥だったということ。
顧客のニーズを読み違え、競合に先を越され、最終的に契約は白紙に戻りました。
自分がそのチームにいる意味を見出せず、モチベーションは底まで下がっていました。
毎朝会社に行くのが憂鬱で、「自分は必要ない存在なんだ」という気持ちが日に日に強くなっていったのです。
この体験が、後に私がマネジメントする側になった時の大きな教訓となりました。
どんなに経験が浅くても、部下には必ず価値のある視点があるということ。
そして、その視点を活かすも殺すも、上司次第だということです。
学び|任せる勇気が生んだ変化

マネジメント側になって最初に意識したのは「思い切って任せる」ことでした。
あの新人時代の苦い経験があったからこそ、部下には絶対に同じ思いをさせたくないと心に決めていました。
入社2年目の部下、田中さん(仮名)に重要な顧客への提案資料作成を任せた時のことです。
その顧客は売上の3割を占める大口取引先。
正直、不安もありました。「失敗したらどうしよう」「自分がやった方が確実なのでは」という気持ちもありました。
でも「失敗してもフォローすればいい。それより彼に成長の機会を与えよう」と腹をくくって任せました。
最初の提案は、確かに不十分
データの分析が浅く、顧客の課題に対する提案も表面的。
普通なら「やっぱり経験不足だった」と取り上げてしまうかもしれません。
でも、その時の田中さんの目の色が変わったのです。
彼は必死に勉強を始めました。
業界の専門書を読み漁り、先輩に積極的に質問し、休日も返上で資料を作り直し
私に何度も相談に来て
「ここはどう思いますか?」
「この分析で十分でしょうか?」と確認を求めてきました。
2週間後、完成した提案資料を見て私は驚きました。
私が作るより遥かに優れた内容だったのです。データは詳細で説得力があり、
提案内容も顧客の立場に立った具体的なもの。
何より、彼独自の視点が随所に光っていました。
最終的に、その提案は顧客から高く評価され、新たな案件受注にもつながりました。
その後、田中さんは社内で最も成長の早いメンバーの一人になりました。
他の若手メンバーも彼の変化を見て「自分も頑張ろう」と刺激を受けるようになりました。
「居場所」を感じられたことで、本来の力を発揮できるようになったのです。
そして、その変化はチーム全体に波及していきました。
実践ポイント|居場所を与える方法

では、具体的にどうすれば部下に居場所を与えられるのでしょうか。私が実践してきた方法を、失敗例も含めてお伝えします。
①採用段階から「居場所づくり」は始まっている
実は、部下に居場所を与える最も重要なタイミングは採用段階です。
ここを見落としがちですが、ぶっちゃけ採用でほとんど決まります。
なぜ採用が重要なのか:
私が以前、スキルだけを重視して採用した営業メンバーがいました。
成績は優秀でしたが、チームワークを重視しない性格。
結果的に他のメンバーとの摩擦が絶えず、最終的に退職
一方で、スキルは劣っていても「チームで成果を出したい」という価値観を持つ人を採用した時は、周りのメンバーも刺激を受けて全体のパフォーマンスが向上しました。
採用で確認すべきポイント:
- 伝えたいことを明確に言語化できるか
- やりたいことに対する具体的なビジョンがあるか
- やってほしいことを理解し、共感してくれるか
- チームの一員として機能できそうか
これらを面接でしっかりと確認し、価値観の合う人を採用することで、入社後の「居場所づくり」がスムーズになります。
②挨拶・雑談で空気を柔らかく

「最近どう?元気してる?」 「おー、おはよう!」
まずは上司側から積極的にコミュニケーションを取ることが重要です。部下が緊張していても、こちらから声をかけることで空気が柔らかくなります。
ただし、ここで失敗した経験があります。ある新人に「彼女はできた?」と聞いたところ、相手がLGBTQの当事者で、とても嫌な思いをさせてしまいました。プライベートに踏み込む時は、細心の注意が必要です。
安全な雑談の例:
- 「最近どう?」
- 「今日は早く来たね」
- 「昨日の残業、お疲れさま」
- 「今朝の電車、混んでた?」
相手の反応を見ながら、徐々に距離を縮めていくことが大切です。
③仕事を任せて自負心を育てる
明確に責任を与えることで、部下は「自分はここに必要な存在だ」と感じられます。ただし、いきなり重要な仕事を任せるのではなく、段階的に進めることが重要です。
段階的な任せ方の例:
- 最初は小さな業務から(議事録作成、データ集計など)
- 少し責任のある仕事(顧客への資料送付、簡単な提案書作成)
- 重要度の高い業務(プレゼンテーション、重要顧客との打ち合わせ)
進捗確認も大切です。「どう?順調?」「何か困ってることない?」と
声をかけることで、部下は「見守られている」安心感を得られます。
ただし、マイクロマネジメントは逆効果。
1日に何度も確認するのではなく、適切なタイミングで声をかけましょう。
④否定せず「じゃあどうする?」と促す

部下が間違った判断をした時
頭ごなしに否定するのではなく
「なるほど、そういう考え方もあるね。じゃあどうする?」と考えさせることが大切です。
悪い例: 「それは違う。正解はこうだ。」
良い例: 「面白い視点だね。ただ、お客様の立場だとどう感じるかな?」 「その方法だと、どんなリスクがありそう?」 「他にも選択肢があるとしたら、何があると思う?」
失敗を責めるのではなく、一緒に改善策を考える姿勢を見せることで、部下は「失敗しても大丈夫」という安心感を持てるようになります。
⑤上司から積極的に声をかける
部下から声をかけてくるのを待つのではなく、上司から積極的にコミュニケーションを取りましょう。
「何か困ってることない?」
「この件、どう思う?」
「最近の調子はどう?」
私が心がけているのは、1日に最低1回は各部下と会話することです。忙しい日でも「お疲れさま」の一言だけは必ず声をかけます。
そっけない挨拶をする上司など、ありえません。部下の成長を本気で願うなら、まず自分から歩み寄ることです。
⑥部下の変化によく気づいてあげる

部下の小さな変化に気づくことも、居場所づくりには欠かせません。私が意識しているのは以下のポイントです。
表情や調子の変化を見逃さない:
- 「今日は元気がないね、何かあった?」
- 「表情が明るくなったね、何かいいことでもあった?」
- 「声のトーンがいつもと違うけど、体調は大丈夫?」
以前、いつも明るい部下が急に無口になった時がありました。
声をかけてみると、家庭の事情で悩んでいることが判明。
仕事の配分を調整し、必要に応じて休暇を取れるよう配慮しました。
見た目の変化にも注意を払う:
- 「髪型変えた?似合ってるね」
- 「新しいスーツ?素敵だね」
- 「最近疲れてそうだけど、大丈夫?」
ただし、容姿に関するコメントは慎重に。ポジティブな変化は褒めても、ネガティブな指摘は避けましょう。
⑦できたことはしっかり喜んであげる
部下が何かを達成した時、どんなに小さなことでも一緒に喜ぶことが重要です。
成果を認める具体例:
- 「資料作成お疲れさま!すごく分かりやすくまとまってるね」
- 「昨日のプレゼン、堂々としてて格好良かったよ」
- 「この改善提案、本当に助かった。ありがとう」
私が印象的だったのは、新人の佐藤さん(仮名)が初めて顧客から直接感謝の言葉をもらった時のことです。報告を受けた瞬間、私は手を叩いて「やったね!」と声に出して喜びました。
その時の佐藤さんの嬉しそうな顔は今でも忘れません。**「一緒に喜んでくれる人がいる」**ということが、部下にとってどれほど大きな励みになるかを実感した瞬間でした。
目に見える形で褒める環境づくり:

言葉だけでなく、視覚的に成果を認める仕組みも効果的です。私のオフィスでは以下のような取り組みをしています。
- 成果掲示板の設置:月間MVPや優秀な提案を事務所に掲示
- ランキング形式での表示:売上成績や改善提案数をグラフで可視化
- 表彰状の授与:四半期ごとに頑張った人に正式な表彰状を贈呈
- 写真付きでの紹介:顧客から感謝された事例を写真と共に掲示
特に効果的だったのは、月1回の「MVP表彰」です。
売上だけでなく、
「チームワーク賞」
「改善提案賞」
「新人成長賞」など多角的な評価軸を設けることで、様々なタイプの部下が表彰されるようになりました。
表彰された部下の家族が事務所を訪れた時、掲示板を見て「息子が頑張ってるのが分かって嬉しい」と涙を流されたことがあります。
目に見える形での評価は、部下本人だけでなく、家族にとっても誇りになるのだと実感しました。
喜びを共有するコツ:
- 感情を込めて反応する(「すごいじゃん!」「やったね!」)
- 具体的に何が良かったかを伝える
- 他のメンバーにも成果を共有する
- 小さな成功も見逃さない
- 視覚的に成果を残す仕組みを作る
実践のコツ:
- 毎朝のタイムカードの時間帯に立ち会う
- ランチタイムに声をかける
- 帰宅時に「お疲れさま」と声をかける
- 週1回は1on1の時間を作る
- 部下の表情や様子を日々観察する
- 成果や成長を見つけたらその場で褒める
継続することで、部下との信頼関係は確実に深まっていきます。
まとめ|信頼関係が成長を引き出す

部下に居場所を与えることの本質は、
しかし、この信頼関係は一朝一夕には築けません。
私自身、最初はうまくいかないことも多くありました。
ある部下に重要な仕事を任せたところ、期待していた成果が出ずに顧客からクレームを受けたことがあります。
その時、私は一瞬
でも、その部下と話し合った時に気づいたのです。
彼は失敗を恐れて、途中で判断に迷った時に相談してこなかった。
「任されたのだから、全部自分でやらなければ」と思い込んでいたのです。
そこで私は、
任せることは、責任を与えると同時に、適切なサポートを提供することでもあります。
定期的な確認、困った時の相談体制、失敗した時のフォロー
これらすべてが「居場所づくり」の一部なのです。
居場所があるから、部下は失敗を恐れずに挑戦できます。
信頼している上司の言葉には重みがあり、部下の心に響きます。
そして、その信頼関係こそが、チーム全体のパフォーマンス向上につながるのです。
現在、私が事業を運営する中でも、この考え方は変わっていません。スタッフ一人ひとりが「自分はここに必要な存在だ」と感じられる環境づくりを最優先にしています。
任せることには勇気が必要です。
でも、その勇気が部下の成長を引き出し、結果的にチーム全体の成果向上につながる。
これは、私が20年かけて学んだ、最も価値のある教訓の一つです。
部下のモチベーションを引き出すのは、最終的には部下自身です。
でも、そのきっかけを作るのは上司の役割。まずは「居場所」を作ることから始めてみませんか。
みなさんへ
あなたの職場では、部下やメンバーに居場所を与えられていますか?
ここまで読んで「そんなことまでやるの?めんどくさいな」と思った方もいるでしょう。
気持ちはよく分かります。私も最初はそう思っていました。
なぜかって?
部下が自立して動いてくれるようになるから
居場所を感じた部下は、指示待ちをやめて自分で考えるようになります
質問の質も上がるし、提案も積極的にしてくれる。
結果として、マイクロマネジメントが不要になって、あなたの負担は格段に減りますよね。
実際の変化:
- 指示出しの時間:1日2時間 → 30分
- 部下からの質問:「どうすればいいですか?」→「こう進めようと思うんですが、どうでしょう?」
- あなたの役割:作業者 → 本来のマネージャー業務
最初は手間でも、3ヶ月続ければ必ず変化が見えてきます。そして半年後には「あの時頑張って良かった」と思えるはずですよ。
もし思い当たることがあるなら、まずは小さなことから始めてみてください。
たった一言の挨拶が、部下の一日を変える可能性があるんです。
そして、小さな仕事でもいいので「これ、君に任せたい」と伝えてみてください。
信頼関係は一日では築けないけれど、毎日の積み重ねが必ず実を結びます。